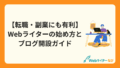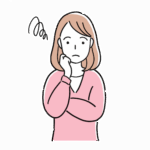
「ブログを書いているけれど、誰に向けて書けばいいのか分からない…」
ブログ初心者の多くが一度はこのような経験をします。
その解決策となるのが「ペルソナ」の設定です。ペルソナを明確にすることで、記事の内容や表現が自然と定まり、読者の心に響く文章が書けるようになります。
そこで本記事では、初心者の方にも分かりやすいように、ペルソナの基本から具体的な作り方、実践的な活用方法まで詳しく解説します。この記事を読めば、自分のブログ記事に最適なペルソナを設定し、読者満足度の高いコンテンツを作るヒントがつかめます。ぜひ最後までご覧ください。
ペルソナとは?初心者にも分かる基本解説

ここでは、ブログにおけるペルソナの基本的な考え方から、「ターゲット」との違い、設定するべき項目まで初心者の方にも理解しやすく説明します。
ブログでいうペルソナとは読者像のこと
ペルソナとは、「自分の記事を読む典型的な読者」を具体的にイメージした人物像のことです。
単に「30代前半の女性」といった属性だけを設定するのではありません。性別・年齢・職業などの基本情報に加えて、その人が抱えている悩みや記事を読む目的、さらには日常の行動パターンまで想定します。
たとえば、料理ブログのペルソナなら以下のように設定します。
32歳女性、共働きで5歳の子どもがいる
平日の夕食は自分が作るが準備時間は30分〜1時間程度・栄養バランスの取れた時短レシピを探している
「誰のための記事か」を明確にすることで、読者の心に刺さる内容を作れるようになります。
ターゲットとペルソナの違い
マーケティング用語に「ターゲット」という言葉もありますが、「ターゲット」は属性を広く定義したものです。たとえば「20代女性」「主婦層」「ビジネスマン」といった、グループ全体を指します。
一方ペルソナは、そのターゲットの中から代表的な1人を深掘りしたものです。「28歳男性・営業職・残業が多く自由な時間が少ない・副業に興味があるが何から始めればいいか分からない」といった具合です。
- ターゲット:属性を広く定義。マーケティング戦略の方向性を決めるために使う。
- ペルソナ:具体的に設定。ニーズの把握や施策・表現を決める際に利用する。
ブログ運営においては、ペルソナを設定することで読者の検索意図や共感ポイントをより具体的に想像しやすくなります。
ブログペルソナの基本項目
ブログでペルソナを設定する際は、以下の要素を押さえておきましょう。
属性:年齢・性別・職業
属性は、読者が置かれている状況や価値観を推測する手がかりになります。ブログでペルソナの属性を決める際には、家族構成やライフスタイル、普段よく使うサービスなどは不要です。
その代わりに、以下の項目を設定します。
ブログで設定する項目:現状の悩みや課題、検索経緯、理想の状態・目的
読者は何かしらの問題を解決したくて検索しています。その経緯や悩み、解決後にどうなりたいかを明確にすることが大切です。こうすることで、より実践的なペルソナ設計ができます。
理想は、上記の項目をバラバラに設定するのではなく、ストーリー性を持たせて一人の人物像として設定することです。「こういう背景があって、こんな悩みを抱えていて、だからこそこの記事を必要としている」という流れで考えると、リアルなペルソナが作れます。
ペルソナの例
例えば、この記事のペルソナは以下のように設定しています。
24歳、男性。メーカー勤務の営業職
副業でWebライティングを始めようと、ブログでSEO記事を書くための練習をしている。2〜3記事作成してみたが、読者に役立つ記事が書けているような感じがしない。読者に刺さる記事を書く方法を調べていたところ、ペルソナを設定することが重要だと知った。ただ、具体的にどのように設定したら良いかわからない。そこで「ブログ ペルソナ」と検索してみた。
これくらい読者像が明確にできれば、ブログ記事のペルソナとしては十分です。
ペルソナは1記事ごとに設定する

ペルソナ設定で重要なのは、ブログ全体で一つのペルソナを決めるのではなく、記事(=キーワード)ごとに想定読者を明確にすることです。
同じテーマを扱っていても、検索意図は人によって大きく異なります。たとえば「転職 ブログ」というキーワードで考えてみましょう。ある人は転職体験談を読みたくて検索し、別の人は転職活動のノウハウを知りたくて検索しているかもしれません。
各記事に合ったペルソナを設定することで、内容の方向性がブレず、読者の満足度を高めることができます。
また、一貫した読者像に対する構成を設計することは、検索エンジンからの評価においてプラスに働きます。たとえば、Googleは「検索者の意図に合致したコンテンツ」を高く評価します。ペルソナに基づいた記事作りは検索順位の向上につながりやすいです。
ペルソナを設定する3つの効果
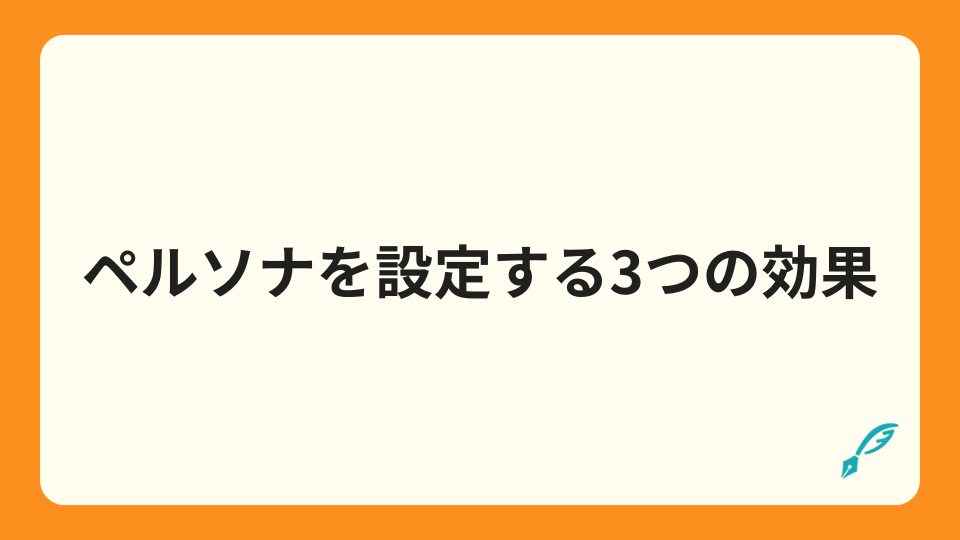
ペルソナ設定が重要だと理解しても、実際にどんなメリットがあるのか具体的にイメージできないかもしれません。ここでは、ペルソナを設定する以下の3つの効果について解説します。
- 何を書けばいいかが明確になる
- 読者に共感される記事が増える
- 記事のトーンや言葉遣いが統一される
何を書けばいいかが明確になる
ペルソナが決まると、記事のテーマ・切り口・構成が自然と定まります。
「このペルソナは、どんな情報を求めているだろう?」と考えることで、書くべき情報と不要な情報の判断がしやすくなるのです。結果、無駄な内容が減り、読者にとって本当に価値のある記事を作れます。
「副業でライティングを始めたばかりの初心者」がペルソナの場合
専門的なSEOの知識よりも「まず何から始めればいいか」「どうやって案件を獲得するか」といった実践的な情報が求められるでしょう。
このように、記事の内容が具体的になり「何を書くか」に迷わなくなります。
読者に共感される記事が増える
ペルソナを深く理解すると、読者の悩みや感情に寄り添った表現ができるようになります。「自分のことだ」と感じてもらえるような記事は、滞在時間が長くなったり、SNSでシェアされたりする可能性も高まります。
また「このブログは自分のことを分かってくれる」と感じた読者は、リピート訪問してくれますし、ファンとして定着してくれやすいです。
記事のトーンや言葉遣いが統一される
ペルソナを意識すると、文体(敬語かカジュアルか)や語彙レベルを適切に統一できます。
たとえば、子育て中の女性向けなら柔らかく親しみやすい口調が適しているでしょう。一方、ビジネス層向けなら論理的で簡潔なトーンが好まれます。
ペルソナに合わせた一貫した文体で書くことで、読者は違和感なく記事を読み進められます。記事中でトーンがバラバラだと、読者は「この記事は誰に向けて書いているの?」と混乱してしまうのです。
【実践ステップ】ブログ記事のペルソナを作る方法

ここからは、初心者でも実践できるペルソナの作り方を紹介します。
1. キーワードを決める
ペルソナを設定する前に、記事で狙う検索キーワードを決めることが必要です。どんなキーワードで検索されたいかが決まっていなければ、どんな読者を想定すればいいかも定まりません。
たとえば「副業 webライティング 初心者」というキーワードを狙うなら、ペルソナは「副業でWebライティングを始めたい初心者」となります。キーワードには読者の意図が凝縮されているのです。
まずは、記事のテーマに合ったキーワードをしっかり定めましょう。
キーワード選定がまだの方は、キーワード選定の方法について解説した記事をご覧ください。
2. キーワードで検索しそうな人物の属性を想像する
キーワードが決まったら、次はそのキーワードを入力しそうな人物の属性を考えます。
年齢・性別・職業について、どんな人がこの言葉で検索するのかを具体的に想像してみましょう。検索している瞬間の状況まで思い浮かべると、よりリアルなペルソナになります。
例えば「副業 ライティング 始め方」で検索する人なら、「副業でライティングを始めたばかりの20代後半の会社員」かもしれませんし、「趣味ブログを収益化したい30代の主婦」かもしれません。
キーワードから読者像を逆算するとペルソナの輪郭を作れます。
3. 検索に至るまでの経緯を考える
ペルソナをより具体的にするには、その人がどんな悩みや課題を抱えて、どんな経路で検索したかを想像することが重要です。
たとえば「ブログ ペルソナ 作り方」で検索する人の場合、「ブログを始めたがアクセスが伸びない→原因を調べる→ペルソナという言葉を知る→具体的な作り方を検索」といった流れが想像できます。
背景の理解が深いほど、読者に響く構成を作れますし、記事で解説すべきポイントを自然に決められます。
4.知って実現したいことを明らかにする
ペルソナ設定の最終ステップは、記事を読んだあとに読者が何をしたいかまで想定することです。たとえば「自分のブログでペルソナを設定して、アクセスを増やしたい」「読者に共感される記事を書いて、ファンになってもらいたい」といった具合です。
このゴールを意識することで、記事の設計に一貫性が生まれます。どんな情報を、どの順番で提示すれば、読者が行動しやすいかが分かるでしょう。それに伴って内部リンクの配置やCTAの設計も、ペルソナのゴールに合わせて最適化できます。
Call to Action(行動喚起)の略。読者に具体的な行動を促すための呼びかけのことです。記事の最後や途中に設置される、「資料請求はこちら」「関連記事を読む」などのボタンや文章を指し、読者を次のステップ(クリック・登録・購入など)へ導く役割がある。
読者が記事を読み終えた後、どんな未来を実現したいのか。そこまで考え抜くことが、本当に役立つコンテンツを作る秘訣です。
生成AIでペルソナを作成するのもあり
ChatGPTなどの生成AIを使って、キーワードからペルソナ案を出してもらう方法も有効です。
生成AIで「〇〇というキーワードで検索する人のペルソナを3人作成して」と指示すれば、短時間で複数のパターンを提案してくれます。時間の節約になりますし、自分では思いつかなかった視点を得ることが可能です。
ただし、AIが出力したものをそのまま使うのはおすすめしません。あくまで叩き台として活用し、自分の経験を分析もとに修正して利用してください。
設定したペルソナの活用方法
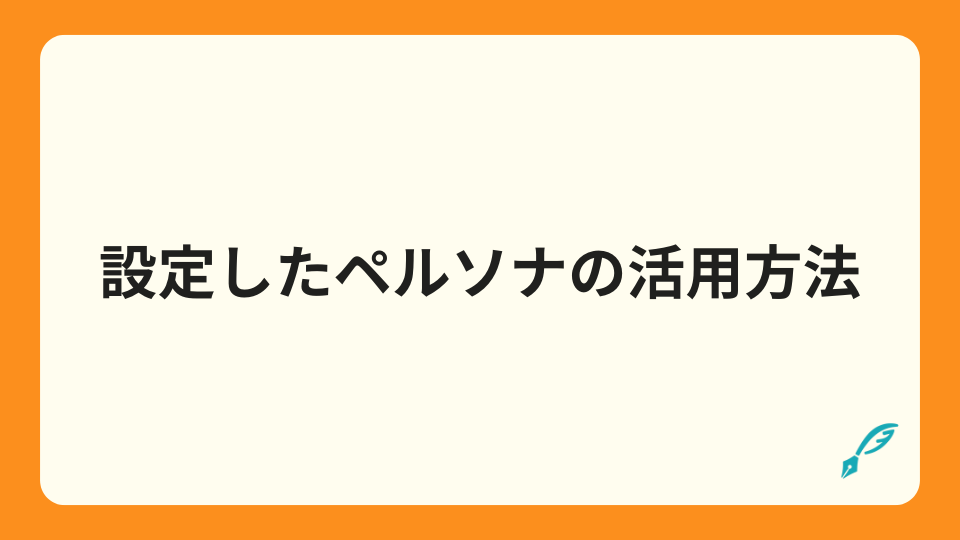
最後に、設定したペルソナを実際の記事作成でどう活用するか、具体的な方法を紹介します。
検索意図を考える
まず、ペルソナが検索で何を知りたいのかを洗い出しましょう。
検索意図は大きく分けて、「情報を調べたいだけ」「複数の選択肢を比較したい」「購入や行動を迷っていて背中を押してほしい」などのパターンがあります。たとえば「夕食 簡単」で検索する人は、簡単な夕食の献立だけでなくレシピも求めているはずです。
検索意図が考えられたら、そこから記事構成を作ることができます。
また、検索意図を把握すると、タイトル・見出し・導入文を適切に設計できます。読者が求めている答えを、求めている形で提供できるようになるのです。
検索意図について詳しく解説した記事もご覧ください。
リード文で共感を得る
ペルソナの悩みや感情を想定することで、リード文(導入文)で共感を生みやすくなります。読者が検索に至るまでの背景を理解していれば、「あなたもこんな悩みを抱えていませんか?」という形で自然に問題提起することが可能です。
たとえば、副業ライター向けの記事なら、導入文は以下のようになります。
「副業でブログを始めたけれど、誰に向けて書けばいいのか分からない…そんな悩みはありませんか?実は、多くの初心者ブロガーが同じ壁にぶつかっています。」
この一文で読者は「自分のことだ」と感じ、記事を読み進める動機が生まれます。
ペルソナを設定することで、「共感→解決策提示→本文導入」という流れが自然に作れるようになるでしょう。
盛り込む内容や表現の参考にする
ペルソナが決まっていれば、知識レベルに合わせて説明の深さや言葉づかいを決めやすいです。
初心者向けなら専門用語を使う際には必ず解説を加え、できるだけ平易な表現を心がけます。一方、上級者向けなら基礎的な説明は最小限にし、実例や応用テクニックを中心に構成にします。
ペルソナを意識することで、表現やトーンに一貫性を保てます。ペルソナは単なる事前準備ではなく、記事作成のすべての作業で指針になるでしょう。
まとめ
ブログ記事では、ペルソナを設定し、読者の検索意図・感情・目的を丁寧に掘り下げることで、質の高いコンテンツを作ることができます。読者の満足度が高まって、ブログサイトを再訪問してくれたり、検索エンジンからの評価が向上したりするでしょう。
まずは次に書く記事で、今回紹介したステップに沿ってペルソナを設定してみてください。なかなかうまく作れない時は、生成AIなどのツールも利用してみましょう。