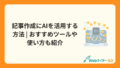「ブログの検索意図って何なの?」
「検索意図の調べ方を教えて欲しい」
「記事に取り入れる方法も知りたい!」
このような悩みを解決できる記事になっています。
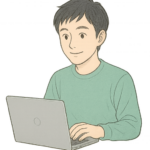
筆者の私は、これまでWebマーケティング会社と個人の両方でWebライターを5年経験し、多くの上位記事を執筆してきました。
この記事で紹介する検索意図の分析方法を理解して、記事に反映すればより多くの人にブログ記事が読まれるようになります。
記事の前半部分では、検索意図の定義や分析方法を、後半では検索意図の記事に反映する方法を実践ワークとともに紹介するので、じっくり読んでください。
ブログの検索意図とは?なぜSEOに重要なのか

そもそもブログの検索意図とは何なのか、定義やブログ記事にとって大事な理由、さらにSEO対策に欠かせない理由を解説します。
検索意図の定義:ユーザーが検索した理由・課題のこと
ブログ運営やSEO対策を考えるとき、必ず意識すべきなのが「検索意図」です。検索意図とは、ユーザーが検索キーワードを入力した背景にある理由や本当に解決したい課題のことを指します。
Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)の略。検索エンジンに自分たちのコンテンツを適切に評価してもらう施策や取り組みのこと。
たとえば、「ブログ 始め方」と検索する人は「ブログの始め方を知りたい」という情報収集が目的です。また、「ブログ テーマ 購入」と検索する人は「ブログのテーマを購入したい」という行動意図を持っています。
ブログでは、このような検索意図を満たす記事を書く必要があります。
顕在意図と潜在意図
検索意図には、「顕在意図」と「潜在意図」の2種類があります。
顕在意図とは、ユーザーが自分で自覚している目的です。
たとえば「ブログ 始め方」と検索する人は、「ブログを開設する手順を知りたい」という明確な意図を持っています。記事では、この「手順を知りたい」というニーズをストレートに満たす内容(例:開設方法・必要なツール・費用など)を提供することが重要です。
一方で、潜在意図はユーザー自身がまだ言語化できていない裏にあるニーズを指します。
先ほどの例なら、ユーザーは「ブログで収益を得たい」「挫折せずに続けたい」といった本音を持っていることが多いです。
こうした潜在意図にまで踏み込むと、読者の共感を得られるだけでなく、「この記事は自分の気持ちを理解してくれている」と感じてもらえるようになります。
検索意図を無視したブログが読まれない根本原因
検索意図を無視して記事を書くと、ユーザーが求める答えにたどり着けず「知りたいことが書かれていない」と離脱されてしまいます。
失敗するケースとしては、「購入意図があるキーワードに対して、解説記事だけ出している」「求めている回答を先延ばしにする」「具体的な行動手順や信頼できる根拠がない」などです。その結果、訪問数や滞在時間が減り、評価されにくくなります。
どれだけ時間をかけて長文で丁寧に書いたとしても、読者の疑問や目的とズレていれば「読まれないブログ」になってしまうのです。
Googleが検索意図を重視する2つの理由:「ユーザーファースト」と「コンテンツ評価」
Googleが検索意図を特に重視するのには、大きく分けて2つの理由があります。
1つ目は、ユーザーファーストの原則です。
Googleの使命は「世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるようにすること」(引用:Google会社情報)です。つまり、検索者が最短で知りたい答えにたどり着けることが最優先されます。
もしユーザーが検索しても求めていた情報に出会えなければ、検索体験そのものが悪化し、Googleの信頼性が損なわれます。だからこそ「検索意図に沿ったコンテンツかどうか」が、最重要の評価軸になっているのです。
2つ目は、コンテンツ評価の精度向上です。
Googleは単にキーワードが含まれているかどうかではなく、記事全体がユーザーの意図を満たしているかを多角的に判断しています。内容がユーザーに役立つことはもちろん、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)や網羅性といった評価基準も、最終的には「意図に合致しているかどうか」に結びつきます。
E-E-A-Tとは、Googleがコンテンツを評価するときに重視する4つの基準で、経験(Experience)・専門性(Expertise)・権威性(Authoritativeness)・信頼性(Trustworthiness)の頭文字を取ったものです。記事を書いた人の体験や専門知識、信頼できる情報源であるかどうかが評価のポイントになります。※参考:Google – E-E-A-T と品質評価ガイドラインについて
このように、Googleは「ユーザーに役立つか」という視点と「意図を正しく汲み取ったコンテンツか」という視点の両面から記事を評価しています。したがって、ブロガーやWebライターが、ブログで成果を上げるためには、単なるキーワード対策ではなく「読者の意図に寄り添った記事設計」を意識することが大切です。
クエリと検索意図

検索意図と一口にいっても実際には様々な意図がありますが、主に4つのパターンに分けられます。ブロガーやWebライターが記事を書く際には、この4種類を意識することで、読者の求める情報に的確に応えられるようになります。
クエリはユーザーが検索欄に打ち込む言葉
まず検索意図を理解するためには、ユーザーが入力する「検索クエリ」について知る必要があります。
「クエリ(Query)」とは、英語で「問い合わせ」や「質問」という意味で、ユーザーが何かを調べたいときに検索欄に打ち込む言葉のことを指します。
似た言葉に「キーワード」がありますが、キーワードはユーザーが検索で使用する言葉(クエリ)を単語で区切ったものです。クエリはユーザーが使用する言葉で、同じ意図で使われても、表記ゆれや誤字などが発生します。
マーケティングでは、そのような表記ゆれを無くすために「キーワード」として検索意図を考えることが多く、「クエリ」と「キーワード」はほとんど同じ意図で使われます。
4種類の検索意図と適したコンテンツ
クエリには、行動のサインが隠されています。たとえば「ブログ 始め方」というクエリなら「情報を知りたい」、一方で「ブログ テーマ 購入」といったクエリなら「購入したい」と判断できます。
このクエリを分類すると以下の4種類に分けられます。
| クエリ | 検索意図 | 特徴 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| Knowクエリ | 情報型(Informational) | ユーザーが何かを知りたいときに使用する言葉。疑問や悩みの解決で使われる。 | 「SEOとは」「赤ワイン 種類」「英検 勉強方法」など |
| Doクエリ | 案内型(Navigational) | ユーザーが何かをしたいときに使用する言葉。自分の行動の参考やヒントに使われる。 | 「チケット 申し込み」「肉じゃが レシピ」など |
| Goクエリ | エリア型(visit in person) | ユーザーがどこかに行きたいときに使用する言葉。固有名詞が多い。 | 「東京駅 ラーメン」「〇〇市 内科」など |
| Buyクエリ | 取引型(transactional) | ユーザーが何か購入したいときに使用する言葉。「商品名」や「おすすめ」「ランキング」などの単語が使われる。 | 「掃除機 軽い おすすめ」「格安航空券 比較」「Wi-Fi ランキング」など |
情報型(Informational)
知識を得ることが目的の検索です。読者は情報を理解したい段階にあるため、解説記事やノウハウ記事が適しています。
案内型(Navigational)
自分の行動の参考やヒントにしたいときに検索される言葉です。他にも、特定のサイトやサービスにたどり着きたいときに使われます。公式サイトや目的のページにスムーズに誘導するコンテンツが求められます。
エリア型(visit in person)
特定の場所に行きたいときに使用されます。店舗・施設の紹介記事や、地図・アクセス情報を組み込んだコンテンツが最適です。
取引型(Transactional)
何かを購入する行動につながる検索意図です。商品比較やレビュー記事、申込ページへの導線を設計することが重要です。
この4つを理解すると、単に「キーワードに沿って書く」だけでなく、読者の検索段階に応じた最適な記事構成を設計できるようになります。結果としてSEO評価が上がるだけでなく、読者満足度や成果(購入・登録など)も向上するでしょう。
ブログの検索意図を分析する5つの方法
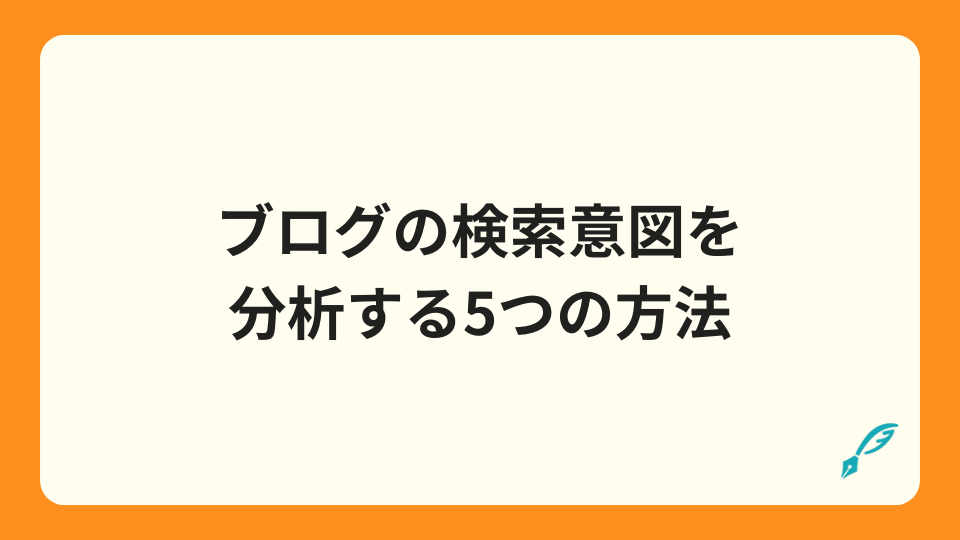
では、実際にこれらの検索意図を調査・分析する方法を紹介します。
1. 自分の頭で考える
一つ目は自分で考えることです。検索キーワードから考えられる、ユーザーが求めていることを考えてみましょう。
最初から何かに頼るのではなく自分の頭で考えることは、記事の独自性を出すためにも重要です。キーワードを検索している人の姿や背景を想像して、求めている情報は何かを洗い出してみてください。
2. 検索して上位10記事のタイトルと見出しを調査する
次の方法は、実際に自分で検索してみて上位の記事を分析する方法です。検索結果上位10記事のタイトルや見出しを確認して、どのような内容を中心に書かれているのかを調べてみてください。
すでに上位に表示されているコンテンツには、その理由があります。上から順番に10個程度のWebページをみることで、Googleの評価基準を把握することが可能です。また、競合のサイトをみることで、抜けている視点や盛り込むべき最新の情報なども出てくるかもしれません。
少し手間がかかりますが、ブログ記事で上位を獲得するために必要な作業なので、手を抜かずに取り組みましょう。
3. 検索結果下部の「関連キーワード」で横断的なニーズを調べる
Google検索エンジンでキーワード検索して、下にスクロールすると「こちらも検索」という関連キーワードが表示されます。

例えば、「ブログ 始め方」で検索してみると「ブログ 始め方 無料」というキーワードが表示されます。このことから、同じ記事内で「WordPressなどの有料で始める方法」と「無料ブログを利用する方法」を解説することで、横断的なニーズに応えることが可能です。
このように、関連キーワードには似たような検索意図が含まれているので、記事内容の参考にすることもできます。
4. キーワードツールで共起語を調べる
検索意図をより深く理解するためには、キーワードに関連してよく使われる「共起語」を調べるのも効果的です。共起語を把握すると、ユーザーが知りたい情報の文脈を掴むことができます。
あるキーワードと一緒に出現しやすい言葉のこと。
たとえば「ブログ 始め方」と調べると、「WordPress」「無料」「テーマ」「収益化」といった単語が頻出します。「ブログの始め方を知りたいだけではなく、WordPressを利用したブログの始め方や無料ブログの作り方、テーマの設定、収益化の方法も求めている」といった裏側のニーズを発見できるのです。
共起語を調べる際は、ラッコキーワードなどのツールの使用をおすすめします。
5. Yahoo!知恵袋やQ&Aサイトでユーザーの「生の声」から悩みを特定
Yahoo!知恵袋や各種Q&Aサイトなどでは、ユーザーがリアルに感じている疑問や不安がそのまま投稿されているため、検索キーワードから読み取れない生の声を拾うことができます。
筆者の私も、キーワードから検索意図を想像しにくいときはQ&Aサイトを頻繁に活用しています。
さらに、Q&Aサイトで頻出する悩みは「検索ボリュームが少なくても潜在ニーズが強いテーマ」である可能性が高く、他の記事と差別化するための切り口としても有効です。
検索意図をブログ記事に反映させる5つのステップ
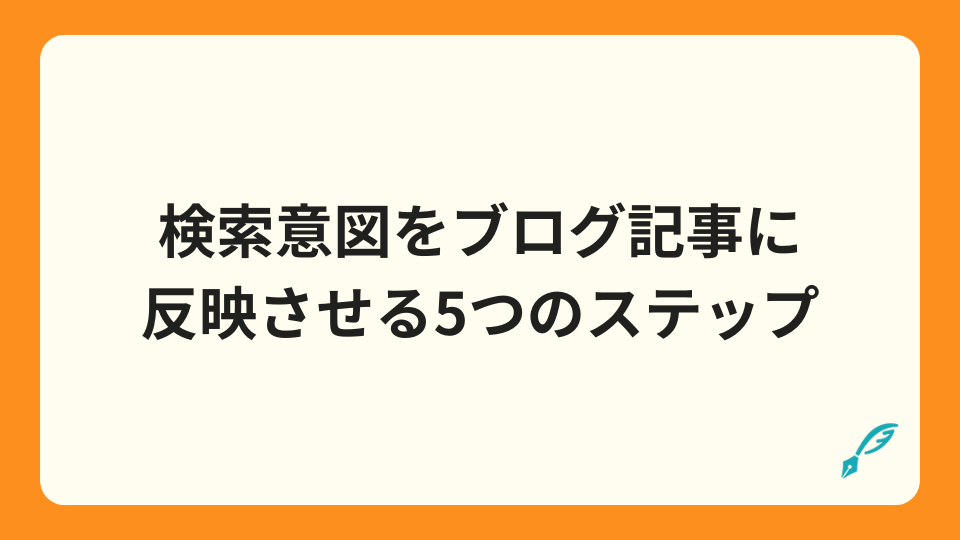
ステップ1:キーワードから検索意図を洗い出す
まずは、書きたい内容に関するキーワードを決めて、そのキーワードから考えられる検索意図を洗い出します。
「記事にするキーワードがよく分からない」場合は、そもそもキーワード選定について理解する必要があります。キーワード選定のやり方を解説した記事を最初からご覧ください。
「キーワード選定は済んでいるけど、どのようなキーワードで記事を書いていけば良いか分からない」場合は、記事にするキーワードを選ぶ基準についての解説をご覧ください。
たとえば、この記事では「ブログ 検索意図」というキーワードを元に記事を作成していますが、以下のような検索意図を洗い出しています。
- 検索意図とは何なのか知りたい
- なぜ検索意図が重要か知りたい
- 検索意図の分析方法を知りたい
- 記事に取り入れる方法を知りたい
- 検索意図の種類やパターンを知りたい
- 読者目線で記事を書くスキルを身につけたい
ステップ2:見出しに検索意図を漏れなく盛り込み、網羅性を高める
続いて、検索意図を踏まえた見出しを作成します。
ブログ記事の見出し(H2・H3)は、検索意図を具体的に反映させる最も重要な部分です。検索ユーザーは、記事全体を細かく読む前に「見出し」をざっと見て、自分が求めている情報があるかどうかを判断しています。見出しの設計は、「読者が記事を読むかどうか」を左右する決定要因なのです。
たとえば、この記事での見出し構成は以下のようになっています。
<H2> ブログの検索意図とは?なぜSEOに重要なのか
<H3> 検索意図の定義:ユーザーが検索した理由・課題のこと
<H3> 顕在意図と潜在意図
<H3> 検索意図を無視したブログが読まれない根本原因
<H3> Googleが検索意図を重視する2つの理由:「ユーザーファースト」と「コンテンツ評価」
<H2> クエリと検索意図
<H3> クエリはユーザーが検索欄に打ち込む言葉
<H3> 4種類の検索意図と適したコンテンツ
<H4> 情報型(Informational)
<H4> 案内型(Navigational)
<H4> エリア型(visit in person)
<H4> 取引型(Transactional)
<H2> ブログの検索意図を分析する5つの方法
<H3> 1. 自分の頭で考える
<H3> 2. 検索して上位10記事のタイトルと見出しを調査する
<H3> 3. 検索結果下部の「関連キーワード」で横断的なニーズを調べる
<H3> 4. キーワードツールで共起語を調べる
<H3> 5. Yahoo!知恵袋やQ&Aサイトでユーザーの「生の声」から悩みを特定
<H2> 検索意図をブログ記事に反映させる5つのステップ
<H3> ステップ1:キーワードから検索意図を洗い出す
<H3> ステップ2:見出しに検索意図を漏れなく盛り込み、網羅性を高める
<H3> ステップ3:タイトルに検索意図を含め、読者の注意を引く
<H3> ステップ4:リード文で記事の内容を明確に伝え、離脱を防ぐ
<H3> ステップ5:ユーザーの検索行動の終着点となるコンテンツを目指す
<H2> 【実践ワーク】キーワードから検索意図を分析してみよう
見出しを作る際は、読者が内容を理解しやすいようにすることも心がけ、最も知りたい情報を最初に持ってくるのがポイントです。そしてこの見出しをもとに本文を作成します。
ステップ3:タイトルに検索意図を含め、読者の注意を引く
タイトルは検索結果で最初に目に入る部分です。ここに検索意図に沿ったキーワードを自然に含めることで、ユーザーに「このページなら自分の疑問を解決できそうだ」と認識してもらえます。
以下のポイントに意識してタイトルを作成しましょう。
- 記事を適切に表す
- タイトルにキーワードを含める
- キーワードはできるだけ前方に含める
- 複数の言葉で構成されるキーワードはなるべく順番を変えない
- 読者の疑問や悩みを解決できることが分かるタイトルにする
ステップ4:リード文で記事の内容を明確に伝え、離脱を防ぐ
記事の冒頭のリード文は、読者が本文を読み進めたくなるかを左右する重要なパートです。リード文が曖昧だと、自分の求めている情報ではないと判断されて離脱されます。リード文を作成するときは、以下の2つを盛り込むようにしてください。
- 検索意図から想定できるユーザーの疑問や悩みに共感する
- 記事から得られることを具体的に示す
こうすることで、読者は安心して本文を読み進められます。
ステップ5:ユーザーの検索行動の終着点となるコンテンツを目指す
最終的に理想なのは、読者が「この記事で必要な情報がすべて解決した」と感じ、再検索の必要がなくなる状態です。具体例や図解、関連リソースまで充実させて、検索意図を完全に満たす記事にすることを意識しましょう。
【実践ワーク】キーワードから検索意図を分析してみよう
このパートは、実際にブログ記事を作成するための実践ワークです。ワークの通りに実行することで、検索意図を反映した見出し案まで作成できます。ぜひ手を動かしながら読んでください。
- 1キーワードを決める(2〜3分)
記事にしたいキーワードを一つ決めてください。
- 2キーワードから考えられる検索意図を自分の頭で考える(5分)
キーワードをもとに、検索ユーザーの「顕在意図」と「潜在意図」を自分で考えてみてください。
- 3Yahoo!知恵袋でキーワードを入力して具体的な悩みを確認する(2〜3分)
検索意図が想像しにくい場合、Yahoo!知恵袋でキーワードを検索してみてください。キーワードに関係する、リアルな悩みや疑問が出てくることがあります。
- 4キーワードで検索して上位10記事の見出しを調査する(10〜15分)
実際に、キーワードをもとにGoogle検索エンジンで検索してみてください。そして、検索結果に出てきた上位10個の記事の見出しを見て、自分が考えた検索意図に漏れがないか確認します。
- 5関連キーワードを確認する(1分)
競合記事を確認したら、Google検索エンジンのページ下部に出てくる「こちらも検索」という部分を見て、他のニーズや取り入れるべき内容がないかを確認します。
- 6共起語を調べる(1分)
ラッコキーワードにアクセスして、共起語を調査します。出てきた共起語を上から順番にざっと50個くらい眺めて、検索意図の漏れや内容の文脈を確認してください。
<ラッコキーワードの使い方>
キーワードを入力して、共起語を検索する

出てきた共起語を確認する

- 7洗い出した検索意図を読者の目的を叶えるための順番に並べる(5〜10分)
ここまでの作業をきちんと行えば、盛り込むべき検索意図を網羅できた状態になっています。それらの検索意図をもとに、読者にとってどのような順番にすれば、目的を叶えられるか読みやすいかを考えて、並べ替えてください。
- 8検索意図をもとに見出し案を作成する(5〜10分)
順番が決まったら見出し案を作成します。検索意図に答えることを意識して、見出しを考えてください。納得いかない場合でもあくまで案として考え、執筆時に修正しましょう。
- 9タイトル案を作成する(5分)
見出しと記事内容を表したタイトル案を作成してください。解説したようにキーワードを前方に含めて、クリックしたような内容にしましょう。誇張表現などはNGです。
- 10タイトル案と見出し案を確認する(5分)
タイトル案と見出し案ができたら、洗い出した検索意図に対して抜け漏れがないかを再確認します。これで作業は完了です。
まとめ | 検索意図を理解すれば、読まれるブログ記事が書ける
以上、検索意図について解説しました。初心者の方は、記事で紹介した検索意図の分析を繰り返すことで、だんだん検索意図を踏まえた記事を作れるようになります。最初から完璧を目指す必要はありません。
まずはキーワードを1つ選んで、「このキーワードを検索する人は何を求めているのか?」と考えることから始めましょう。きちんと検索意図を理解することが、読まれるブログを育てるポイントになります。